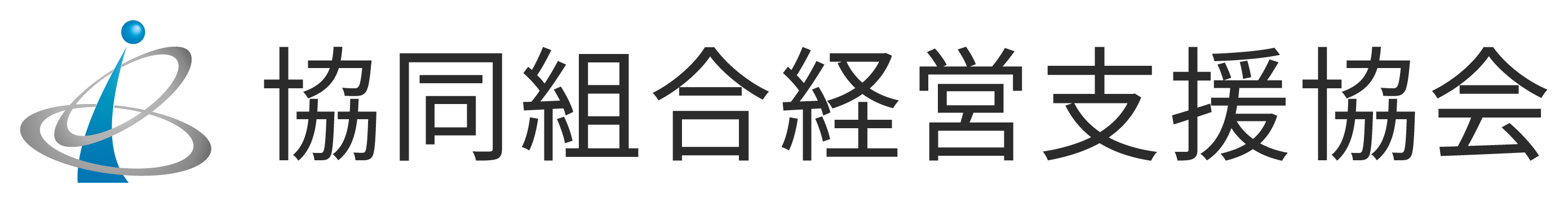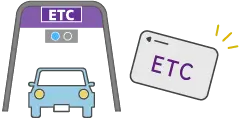職場におけるパワーハラスメント(以下、パワハラ)が深刻な社会問題となっています。厚生労働省の調査によると、労働者の約5人に1人が「過去3年間にパワハラを受けたことがある」と回答しており、多くの職場で見過ごせない実態が明らかになっています。
パワハラは、働く人の尊厳や人格を傷つけ、心身の健康を損なうだけでなく、職場の生産性低下や人材流出、さらには企業の信用失墜にもつながる重大な問題です。
パワーハラスメントとは?
「労働施策総合推進法」では、次の3つの要件をすべて満たす言動を「職場のパワーハラスメント」と定義しています。
- 1.優越的な関係を背景とした言動
- 2.業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの
- 3.労働者の就業環境が害されるもの
上司から部下への行為に限らず、先輩・後輩や同僚間、さらには部下から上司に対して行われる場合も含まれます。
パワーハラスメントの6つの典型的な類型
厚生労働省によると、パワハラには、主に次の6つのタイプがあります。
- 1.精神的な攻撃(脅迫・侮辱・ひどい暴言など)
- 2.身体的な攻撃(暴行・傷害など)
- 3.過大な要求(遂行不可能な仕事の強制など)
- 4.過小な要求(能力・経験に見合わない軽度な仕事のみを与えるなど)
- 5.人間関係からの切り離し(隔離・無視・仲間外しなど)
- 6.個の侵害(私的なことに過度に立ち入る行為)
これらの行為は、いずれも「業務の適正な範囲」を超えたものであり、決して許されるものではありません。
企業にとっての影響
パワハラを放置すれば、被害者のメンタルヘルス悪化だけでなく、職場の雰囲気やチームワークの悪化、生産性の低下といった問題を引き起こします。さらに、企業が「安全配慮義務違反」などで法的責任を問われるケースもあり、訴訟や損害賠償に発展することもあります。
一人の不適切な言動が、組織全体の信頼を揺るがすことになるのです。
防止のために企業が行うべきこと
令和4年(2022年)4月1日から、すべての事業主に「パワーハラスメント防止措置」が義務づけられました。企業は、次のような取組を行う必要があります。
- ・事業主の方針等の明確化および周知・啓発
パワハラ行為を許さない方針を就業規則などで明示し、全社員に周知する。 - ・相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
相談窓口を設け、社員が安心して相談できる環境を整える。 - ・職場におけるパワハラに関する事後の迅速かつ適切な対応
事実関係を速やかに確認し、被害者への配慮や加害者への処分、再発防止策を講じる。 - ・プライバシーの保護と不利益取扱いの禁止
相談者や関係者の秘密を守り、相談したことを理由に不利益な扱いを受けないようにする。
企業だけでなく、職場で働くすべての人の意識が重要です。
パワーハラスメントは、誰にでも起こりうる問題です。もし、自分や周囲に被害が見られる場合は、一人で抱え込まず、早めに相談することが大切です。
<引用:厚生労働省「NOパワハラ」
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000189292.pdf>